こんにちは、transです。
今回は「効率の良い実験レポートの書き方」という題で書いていきます。
理系の人にとって最も重い課題が実験レポートなのではないでしょうか?
筆者もコツをつかむまで、締め切りギリギリまでレポートを書いて、でも成績は取れなくてという最悪な状況に陥っていました。
しかし、コツを掴んでからは、どんなに遅くても前日の夜までには終わりましたし、成績もかなり取れるようになりました。
意識することは、たった3つです。
筆者は化学科の人間なので特に化学科の人は参考になると思います。
それでは行きましょう!
1、誰が何をみるのかを考える
これが、1番大切なことであります。
誰が何をみるのか?
ずばり、教授が学生の能力(成績をつけるため)にレポートを見ます。これを意識するだけで、かなり違います。自己満足のレポートではダメなのです。教授が良い評価をつけるレポートを書かなければならないのです。
では、具体的な方法を説明しておきます。当然でありますが、最も見られる項目は結果と考察です。理由は簡単で、ここが学生によって差が生まれるからです。逆にいえば、極論、それ以外の項目は適当でいいのです。
ここからは各項目ごとに細かく説明していきます。
・緒言
緒言とは、前置きや実験において必要な知識のことです。
緒言では、目的と実験のキーワードについて書くだけで十分です。事実を書くわけですから学生間の差は生まれません。ただし、正確な情報を書いてくださいね。そのために図書館の本なとで調べてください。それが、めんどくさい人用に、筆者のサイトでは実験のキーワードでよく使われることと参考文献を記載するページも作っていくので、そちらも参照して下さい。
あと強いて言うなら、結果で用いる式の説明や導入は書いておいた方がいいと思います(基本的には実験のキーワードで出てくると思いますが)。
・実験方法
実験方法でよくやることは事実に忠実に書き過ぎてしまうことです。
例えば、実験器具の数、「あの手順で何個使って、ここで洗ったから使いまわして」と考える人がいます。
どーでもいい!
いや、そんなところ見ないし(笑)
失礼しました。でも、事実です。実験方法は、最も読まれないです。誰が書いても変わるわけがないものですから。
試薬の重さなどだけ実際に測りとった重さを書いて、あとはサクッと終わらせてしまいましょう。正確に書きすぎる必要はないです。
・結果
ここは、考察に次いで大事な部分です。しっかり書きましょう。特に数値を処理する部分は考え方のプロセス(途中式など)を詳しく書くと、より良いと思います。しっかりやっても、結果は事実を書くだけなので、そこまで時間はかからないと思います。
・考察
最も時間をかけましょう。最も見られますし、最も評価の対象になる部分です。緒言の知識と結果の数字を使って、論理的に自分の考えを述べていきましょう。多少時間がかかってもいい唯一の場所です。感想文ではないので注意してください。
考察の書き方に関しては、詳しい記事を出すので、そちらも参照してください。
・参考文献
インターネットのURLでなければ問題ありません。本を参考文献にして下さい。
詳しい書き方はこちらのリンクを参考にするといいと思います。
筆者のサイトで述べる実験のキーワード等は参考文献も載せるので、それをコピペするのでも問題ありません。
2、先回りする
卒業研究、修士・博士レベルの研究、研究所での研究と学生実験の違いは答えが明確になっているかどうかです。
もちろん、答えが明確な方が学生実験です。
つまり、実験する前から答えが分かっています。
実験が終わってから、実験レポートを書くのでは遅すぎます。
実験をする前に緒言と実験方法は、もちろんのこと、考察も書ける部分は書いてしまうと圧倒的に効率が良いです。
筆者は最終的には、結果の部分も実験値以外は書き終えて、学生実験が終わると、実験値を書き足して、考察を少し手直しして完成というレベルにまで行くことができました。もちろん評価はS(最高成績)を貰っていました。
筆者の例は極端かもしれませんが、緒言と実験方法は実験開始前に終えておきましょう。
3、すぐやる
実験が終わったら、すぐにレポートをやりましょう。その日に書き終えるくらいでも、いいと思います。理由としては、その日起きたことであるので、考察のネタになるようなことも覚えている可能性が高いからです。また、ゆとりを持ってやっておくことで、よりレポートの質を上げることができます。
~まとめ~
効率の良い実験レポートの書き方については以上になります。
今回の記事をまとめると、効率の良い実験レポートを書くためには
「1、誰が何をみるのかを考える」
「2、先回りする」
「3、すぐやる」
の3つを意識することです。
特に、誰が何をみるのかを考えるだけで大きく変わると思います。
結果と考察にできるだけ時間を割いて書いていきましょう。
他の授業、アルバイト、サークルと他にも、たくさんやることがあると思います。なので実験レポートは、すぐに終わらせてしまいましょう。
今回の記事は以上になります。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

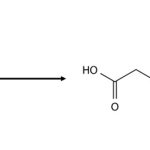




[…] 先ほども述べましたが、成績の9割5分はテストの点数で決まります。なので、テストで点を取ることが最重要事項なのです。バイトやサークル、遊びは、テスト期間中は、一切入れずにテストに集中してください。徹夜も厳禁です。実験レポートも、別記事の効率の良い実験レポートの書き方を参照して、すぐに片づけましょう。 […]