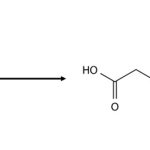こんにちは、transです。
今回は、中和滴定において大切な、中和滴定,Kw値,pHの定義、の3つのキーワードについて解説していきます。
実験の予習をやらなければいけないけど時間が無いという学生に向けて予習の手間が省けるようにこの記事を書いています。スマホで見ながら電車で予習することもできます。実験項目は某大学の実験テキストを参考にしています。
レベル的には、大学の学部生レベルを想定していますが、高校生も化学の発展的なことが知りたければ読んでいただいて構いません。
それでは行きましょう!
1、中和滴定

チューと中和をかけてみました(笑)
まあ、どうでもいいです。
中和滴定とは、ホールピペットを用いて酸(または塩基)を一定体積とり、ビュレットから塩基(または酸)を少しづつ滴下し、中和点(ちょうど中和反応が終わる点)で滴下を止め、それまでに使ったビュレット側の塩基(または酸)の体積を求める操作のことです。
滴下を止めるタイミングとして中和点付近で色の変わる指示薬を加えることが一般的です。
また、片方の物質量(mol)が分かっていれば、中和滴定によって以下の関係式から、もう片方の物質量を求めることができます。
酸の価数×酸の濃度(mol/L)×酸の体積(L)=塩基の価数×塩基の濃度(mol/L)×塩基の体積(L)
また、中和滴定で使う器具には、メスフラスコ,ホールピペット,ビュレット,コニカルビーカーがありますが、トで終わるものを共洗いしてください。
つまり、ホールピペットとビュレットは、トで終わっているので共洗いが必要になります。
以上が中和滴定の簡単なまとめになります。
この章のまとめです。
・中和点を見つけるために指示薬を入れる
・中和滴定によって酸(または塩基)の濃度が求められる
・酸(または塩基)の式は
酸の価数×酸の濃度(mol/L)×酸の体積(L)=塩基の価数×塩基の濃度(mol/L)×塩基の体積(L)
で求められる
2、Kw値

Kw値とは、水のイオン積を示しています。Kは平衡定数、下付き文字のwはwaterを表しています。まあ、水の解離の平衡定数に関連していることを表しているってことですね。
実は、水もわずかですが電離しています。電離式は下のようになります。
H2O ⇄ H+ + OH–
また、この反応の平衡定数は下のようになります。

上記の式の両辺に[H2O]をかけると下のようになります。
K [H2O] = [H+][OH–]
水は基本的に電離しないので[H2O]は一定つまり定数と考えることができます。
なのでK [H2O]をひとまとめの定数Kwとすることができます。
よって以下のような水のイオン積の式を得ることができます。
Kw = [H+][OH–]
水のイオン積は温度によって変化します。例えば、18 ℃では0.74×10-14(mol2/L2)、22 ℃では1.01×10-14(mol2/L2)らしいです。今、図書館がやってないので本が借りられたら正確な値に書き換えておきますね。
しかし、基本的には25 ℃の1.0×10-14(mol2/L2)を使います。
Kw値によってpHも変化してくるので中和滴定において大切な要素であります。
以上がKw値についてになります。
この章のまとめです。
・Kw = [H+][OH–]
・基本的には25 ℃の1.0×10-14(mol2/L2)を使う
3、pHの定義

pHの定義について紹介します。pHは水素イオン濃度で表されます。つまり、以下のような定義になります。
[H+]=1×10-a(mol/L)のとき、pH=a
しかし、さらに発展させた以下の定義で覚えることをお勧めします。
[H+]=n(mol/L)のとき、pH=-log10n
中和滴定を行う上で大切な要素であるので覚えておきましょう。
この章のまとめです。
・[H+]=1×10-a(mol/L)のとき、pH=a
・[H+]=n(mol/L)のとき、pH=-log10n
4、まとめ
いかがでしたか?
今回は、中和滴定のキーワードとして、中和滴定,Kw値,pHの定義について説明しました。
今回の内容を全てまとめると以下のようになります。
・中和点を見つけるために指示薬を入れる
・中和滴定によって酸(または塩基)の濃度が求められる
・酸(または塩基)の式は
酸の価数×酸の濃度(mol/L)×酸の体積(L)=塩基の価数×塩基の濃度(mol/L)×塩基の体積(L)
で求められる
・Kw = [H+][OH–]
・基本的には25 ℃の1.0×10-14(mol2/L2)を使う
・[H+]=1×10-a(mol/L)のとき、pH=a
・[H+]=n(mol/L)のとき、pH=-log10n
また、参考文献は以下の通りになります。
1、辰巳敬(他13名)「化学」数研出版、2012、p 170,171
2、辰巳敬(他9名)「改訂版 化学基礎」数研出版、2016、p 150,151
最後になりますが、参考文献以外はコピペ厳禁です。バレます。気を付けてください。
今回の記事は以上になります。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。